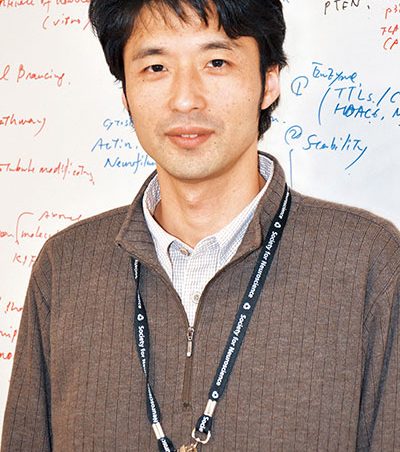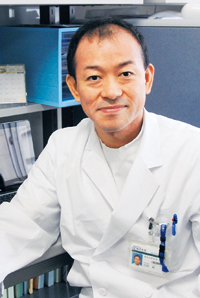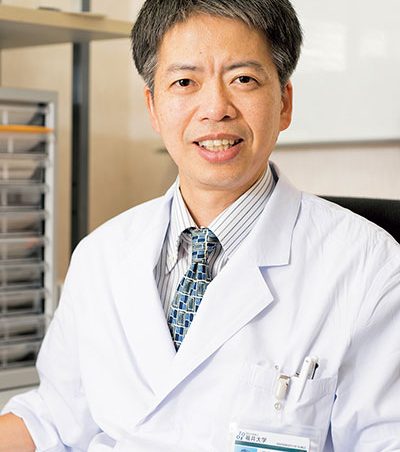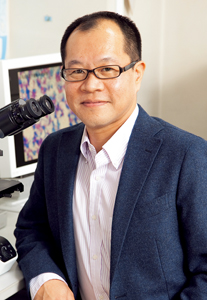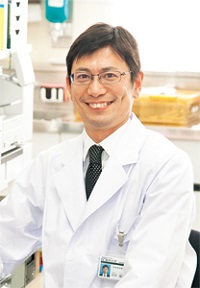生物学
2016年3月15日
白血病患者さんから学び今後に活かす研究を
死に至ることも多い血液のがん「白血病」 白血病は、テレビドラマなどで取り上げられたり、芸能人の方が骨髄移植を受けるなど、話題になったこともあり、聞いたことがある人は多いと思います。白血病は血液のがんで、何かのきっかけで遺伝子が異常を起こし、[...]
2015年11月30日
脳神経細胞を形づくるシステム
生体から学ぶ 今、知能システム工学専攻では、多くの人にとって使いやすく、柔軟なマルチメディアやメカトロニクスをどのように作るかということを課題としています。その一つのアプローチとしてヒトや生物の知能から学ぶことで、これに基づいた新しいシステ[...]
2015年11月30日
エピジェネティックに細胞が多様性を生み出すメカニズム
DNAの謎 ヒトの体はおよそ60兆個の細胞で出来ています。それぞれの細胞は基本的に同じDNAを持ち、同じDNA配列にもかかわらず、手や口や腎臓などまったく違うものができ、複雑な動きや機能までも発達するのか不思議に感じませんか? エピジェネテ[...]
2015年11月30日
放射線による影響を新手法により明らかにする
放射線の生物学 「原子力工学」はひとつの分野に見られがちですが、物理・化学・生物・機械・材料・情報・建築・安全・防災・社会科学など多くの分野による総合科学です。私はその中で、生体が放射線を受けたときの応答や、被ばく線量評価について、分子生物[...]
2015年11月30日
「生物ってすごい!」をものづくりに
カイコからできる絹 ネクタイやスカーフ、着物などの絹製品は保湿性に優れ、しなやかな手触りの繊細な織物で、多くの人に愛されています。絹はカイコが紬ぐ、純天然素材。そんなカイコが繭をつくるまでの不思議なメカニズムに「生物ってすごい!」と興味を惹[...]
2015年11月30日
「いやされない傷」を「いやされる傷」に
4月より本格的なスタートを切った「子どもの発達研究センター」。赤ちゃん世代からの発達について研究する「Age2企画」部門の教授として6月に熊本大学より着任した友田先生にお話を伺いました。先生は小児科医として小児発達学を専門に、主に睡眠・メン[...]
2015年11月30日
生活の質を維持する運動機能を守るために
高齢者に多い変形性膝関節症 高齢になると「膝が痛い」と訴える方は多くいます。そのほとんどは加齢によって内側の軟骨がすり減り、O脚が進行して痛みを生じる、変形性膝関節症と呼ばれる病気です。厚労省の国民生活基礎調査によると全国民のうち2500万[...]
2015年11月30日
難病に苦しむ患者さんを救いたい
皮膚や内臓が固くなり、動かなくなる「全身性強皮症」 重症例では顔面や体幹などの中枢側にも皮膚硬化が拡大してくる。(左) 末梢循環障害の症状として寒冷刺激で指が白くなる。(右) 全身性強皮症は、自己免疫疾患で難病とされる膠原病(こうげんびょう[...]
2015年11月30日
未来の多くの患者さんを救うために
多様な機能を持つ糖鎖 糖鎖は、細胞の表面にある細胞膜に多く存在し、特に細胞のがん化や免疫応答、細菌やウィルス感染による炎症などにおいて重要な役割を演じていることがわかってきており、ここ10年くらいで急速に注目が集まっている研究分野です。私は[...]
2015年11月30日
病後の暮らしをよりよく過ごすために
機能と形態をよりよく整える 平成25年7月、医学部附属病院に形成外科が新設され、それに合わせて赴任してきました。形成外科は、病気やけがなどによって欠損、または変形した身体の組織を「機能的」にも「形態的」にもより自然に近づけることを目的として[...]
2015年11月30日
突然死をもたらす不整脈を克服するために
生命に関わることが多い循環器疾患 平成24年8月に、医学部循環器内科学領域の新設に伴い、赴任しました。循環器領域の疾患は、治療が遅れると生命に関わることも多くあるため、迅速に診断し、適切な治療を行うことが重要です。また、一度危機を脱しても、[...]
2015年11月30日
「心」を可視化する
「心」を生み出す「脳」 私たちの「心」はどのように生まれるのでしょう?洋の東西を問わず、心は 人類共通の興味として探求されてきましたが、技術や科学が進んだ今でも実体は謎に包まれています。喜怒哀楽や思考のように我々が意識できる「心」とそれに伴[...]
2015年11月30日
新しい知見を発見し、医学の進歩に貢献したい
失明原因トップの緑内障 眼科は、日本の科別医師数でも5~6位に入る非常に大きな診療科で、 白内障や緑内障、加齢黄斑変性など高齢者がかかる疾患が多く、糖尿病網膜症のように生活習慣病に分類される疾患も扱うので、日本のような高齢化社会の先進国では[...]
2015年11月30日
自閉症の本質は何か」を問う
増えている自閉症 自閉症の有病率は飛躍的に増えていて、現在は実に学童の2.3%を占めるとされています。しかし、その原因や治療法はまだ明らかになっていません。このため、医療機関および支援機関では社会生活に適応するための訓練を行っていて、これを[...]
2015年11月27日
さまざまな観察で直物の目に見えない実態を掴む!
植物を分類する さて、いきなりですが、キャベツ、ブロッコリー、レタス、カリフラワーの中で系統が異なるものはどれだと思いますか。これらの野菜は小中学校の理科の授業でも触れているものですが、理科教育を学んでいる学生にも難しい問題 です。花や葉の[...]