学生 ☓ 教職員
原子力防災、危機管理の拠点で学ぶ~附属国際原子力工学研究所~
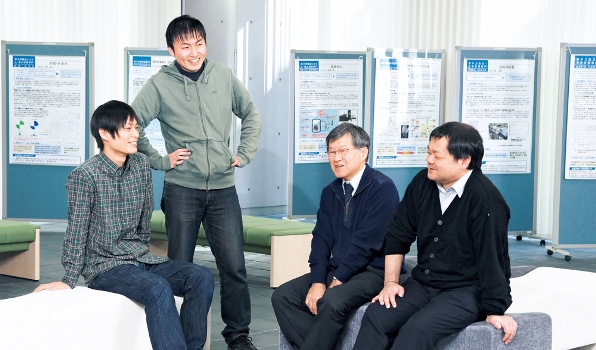
p6_1

~附属国際原子力工学研究所~
「安全と共生」を基本に、世界トップレベルで特色ある原子力人材育成及び研究開発を行う「附属国際原子力工学研究所」。原子力の将来を見据えて新設した「原子力防災・危機管理部門」と、「原子炉構造システム・廃止措置部門」の先生、学生にお話を聞きました。
原子力を総合的に捉える
安田 福島第一原子力発電所(以下、福島第一)の事故を踏まえ、平成24年度に原子力防災・危機管理部門が立ち上がりました。原子力の防災や危機管理に関する研究の他、地元の敦賀市と連携し、地域住民に向けた防災教育や啓発なども行っています。今年度からは、原子炉構造システム・廃止措置部門もできて、柳原先生を中心に研究が進んでいます。
柳原 これまで、原子力分野の研究は、炉の設計や放射線利用などが中心でした。しかし、あのような過酷な事故を受け、防災や廃止措置に対する認識も一層深まったように思います。汚染された福島第一と、その他の原子力発電所では、廃止措置の方法は全く違いますから、私は、両方を視野に入れながら、合理的に問題なく進めていくための研究を行っています。
安田 2つの部門がスタートし、設計から廃止措置まで、原子炉の一生を総合的に捉えることができる機関となりましたね。
松橋 私は福島第一の事故があってはじめて原子力に興味を持ち、進学を決めました。テレビで廃炉問題をよく目にし、実際に調べてみると廃炉について研究している技術者が世界的に非常に少ないことがわかり、それなら自分がやってやろうという気持ちで来ました。今は、廃炉などプロジェクト全体の計画から進捗管理までを行うプロジェクトマネジメントについて研究しています。
地域から海外まで幅広い人々と触れ合う
戸田 私は福井高専で学んでいるときに、原子力のエネルギーの大きさに興味を持ちました。受験勉強をしている最中に福島の事故が起きて、放射線の怖さに改めて気づき、原子力について幅広く学 べる本学に進学しました。今は、放射線が生体に与える影響を中心に研究しています。
松橋 机上のイメージだけで勉強するのは難しいですが、敦賀には原子炉がたくさんあり、実際に現物を見ることができます。また、地域の人たちが原子力分野に非常に関心を持っていて、そういった面でも勉強になりますね。「放射線については分かっているから避難情報を教えて」など、地域の方たちが求めている情報と、自分たちが考えていたことにもギャップがあるんだなと。
戸田 シンポジウムやオープンキャンパスでは、地域の方々に素朴な疑問をたくさん投げかけていただくことで、まだまだ自分たちが学ばなければならないことがたくさんあることに気づかされますね。
安田 日本の原子力事情を知るために、フランスやチェコ、ベトナム、インドネシアやタイといったアジアの国々から、毎年多くの留学生や研究者が学びに来ます。戸田さんや松橋さんのような学生 がメンターとなって、彼らが欲しい情報を英語で提供したり、議論したりします。そのような取組みの中で、語学力だけでなく、物怖じしないマインドなど、世界で活躍できる素養が養われると考えています。
柳原 原子力に限りませんが、今の世の中は、国内だけを見ていてはダメで、グローバルな視野が必要です。いろいろな国の人とコミュニケーションをとる中で、自分の考えを伝えたり、相手の言いたいことを理解したりする力を養い、世界に飛び立ってもらえればと思いますね。この研究所はそういうことができる環境だと思います。
安田 学生たちは、2年間で驚くほど成長しています。大学で学んだことを社会で活かし、またいつか教員として次世代へ思いや知識を伝えてくれることを期待しています。











