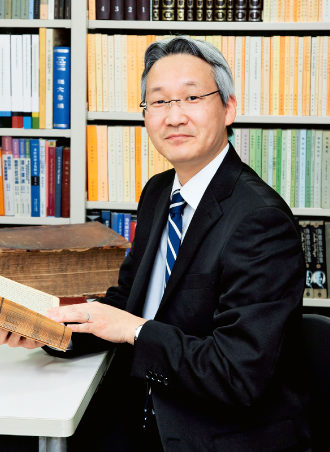芸術・人文社会学
2025年4月9日
哲学と教育をつなぐ推論ネットワーク
道徳教育を哲学でアプローチする 大劇場のステージに立つことを夢見る売れない手品師が、父親が亡くなり母親は働きに出ていて、寂しいという男の子に出会う。手品を見せると、男の子は元気を出し「明日も来てくれる?」と訊ね、手品師は「来るとも」と約束[...]
2024年12月16日
グローバルな視点を持ち 地域活性化を
身の回り 世界につながっている 経済のグローバル化が進展するなか、私たちの身の回りにある様々な製品、例えばスマホや衣服、様々な食料品やエネルギーなどは、供給の流れ、つまりサプライチェーンで世界とつながっています。私たちの生活や、日本のどん[...]
2024年8月5日
「経営学」って役に立つ
会計事務所、事業再生、そして研究の道に 私が会計事務所に入社した1990年代前半は、バブルが崩壊し長く続いた不況の入り口。担当した中小企業は赤字も多く、どうすれば業績が回復するのか、一緒になって考えたことが経営に興味を持ったきっかけです。[...]
2024年4月17日
暴力と警察の問題を 理論的かつ経験的に考える
「貧困」「暴力」を目の当たりに きっかけは大学時代、訪れたブラジル北東部で暴力事件に遭って亡くなったと思わしき方の遺体を目の当たりにした経験です。貧困と暴力が切り離せない形で存在している現実に衝撃を受け、そうした社会で生きるとはどういうこ[...]
2024年4月17日
温故知新 漢文って面白い!
近代化の根底にあった“漢文” 日本は、江戸から明治へと時代が移った際、欧米列強の植民地になることなく、国際社会の仲間入りを果たした稀有な歴史を持っています。私はその基盤の一つが、江戸時代に町人を含む幅広い層に学問が普及していたことだったと[...]
2023年12月18日
暮らしを豊かにする 観光まちづくり
住んでよし、訪れてよし 私の専門は観光学。中でも観光の視点からの「まちづくり」、言い換えると「住んでよし、訪れてよし」の地域づくりのあり方が主な研究テーマです。近年、京都などでは、観光客が殺到してごみの散乱、市民の生活道路の渋滞といった「[...]
2023年8月5日
科学の源流 宗教と切り離せない関係
“正しい地図” への興味から思想研究へ 私の研究テーマは十六世紀ヨーロッパの思想。非常にとっつきにくい分野と思われそうですが、きっかけは建築史を学んでいた学部生の頃、世界の表象の変化に関心を抱いたことです。古代や中世にはユニークな地図が様[...]
2023年8月5日
芸術教育は何を育むのか
仏の“学校参与アーティスト” フランスは「芸術大国」と呼ばれています。それは著名な芸術家を数多く輩出しているから、だけではありません。長い年月をかけてさまざまな芸術が人々の生活の一部となっていて、国をあげてそれを後押しする教育・文化政策を[...]
2023年4月4日
私が福井弁を研究する訳
方言と私 神戸大学に留学していた頃、日本の友人に「飲み物いりますか」と聞くと、「今イラン!」と言われ、なぜ中東の国の名前が?と不思議に思いました。日本語学専攻の私に理解できない日本語がある!ショッキングでした。 卒業後、兵庫県の高校で外[...]
2022年12月13日
まちの変貌 背後にあるものを探究
激動する京都の都心部 私が研究を始めた学生時代は、国内の製造業が衰退する産業空洞化の真っただ中。キャンパスのあった京都市中心部でも繊維関係の事業所などが次々と倒産・閉鎖することで、土地の用途が変化していました。商工業の中心地だったところに[...]
2022年8月16日
効率的な言語学習を 探究する
スピーキング上達のカギは「気づき」 長いあいだ英語を勉強しているのになかなか話せるようにならない、と感じたことはありませんか。それは自分の「上達」に気づけていないことが原因かもしれません。私は母国語以外の言語の習得において、「Awaren[...]
2022年4月4日
生きるために必要な “遊び”のススメ
高専時代から続ける「子どもの遊び」の研究 「子どもの遊び」の研究は、高専時代に卒論のテーマとして指導教員からたまたま提案されたのがきっかけです。建築学科にいた私は、教育学や心理学の分野だと思っていた「遊び」のテーマが、建築空間など環境の課[...]
2022年4月4日
歴史を通して 現代を問い直す
スロヴァキア、翻弄された国に学ぶ 古い歴史のある中央ヨーロッパ東部にあり、1993年に独立したばかりのスロヴァキア共和国。スロヴァキア人は、長らくハプスブルク帝国(オーストリア=ハンガリー二重帝国)の領域内にありながら、言語を共有する者と[...]
2021年8月24日
頭の中に 言葉のネットワークを
楽だけど伝わらない“広い言葉” みなさんは、自分の考えを人に伝えるのは得意ですか?自信を持って得意だと言える人は少ないのではないでしょうか。 人と話している時、感じたことを上手く表現できずとっさに「すごい」や「ヤバい」といった“広い言葉[...]
2019年8月1日
日本語と英語で実は違う 比喩を経て変化する言葉
言語のルーツを辿る 私が英語以外の外国語に触れたのは、中学の音楽の時間で習ったシューベルトの「魔王」です。当時の音楽の先生は「ドイツ語でお父さんは『Vater(ファーター)』。英語の『Father(ファーザー)』に似ているでしょう」と言われ[...]
2018年12月1日
フィールド調査から地域の実態と課題を学び、より良い村づくりや国づくりを考える
途上国での環境利用調査 地形や水の条件をどのように利用して住民は食料を生産し、生計を立てているのか。南アジアの途上国を訪ね、農業的土地利用などの環境利用、またそれに関わる慣行や制度についての調査研究を行っています。 10年ほど前に高地の人々[...]
2018年12月1日
英文学の父 「チョーサー」に魅せられて
過去が見える文学 私は英国の西に位置するウェールズの出身ですが、高校生のころ、父親の転勤でロンドンに移り住みました。そこでジェフリー・チョーサーという14世紀のイギリス詩人の作品に出会い、英文学のおもしろさに引き込まれました。チョーサー文学[...]
2018年8月1日
版画の未来のために 創作環境を整える
身体の不調をきっかけにたどり着いた版画技法 版画というと、小・中学校の授業でも馴染みのある「木版画」を思い浮かべる人が多いと思いますが、他に、銅板や石板を使った版画もあります。 銅版画は、銅板の表面に塗った「グランド」という防蝕膜を鉄筆など[...]
2018年4月6日
文学作品に込められた 移民のアイデンティティについて考える
“The squeaky wheel gets the grease.” これは米国のことわざで、直訳すると「ギシギシ言う車輪は、油を得る」。困ったことがあったら必ず助けを求めなさいという意味です。米国の人間社会は、人種のサラダボウルやパ[...]
2017年3月23日
漢訳聖書から言語の違いを読み取る
文語と口語の使い分けの基準は? 私の専門分野は「中国語学」で、主に19世紀以降の語彙の変遷について、漢訳聖書などを用いて研究しています。聖書を扱うため、キリスト教や聖書自体の研究も必要となります。 中国語の言語体には、大きく分けると書き言葉[...]