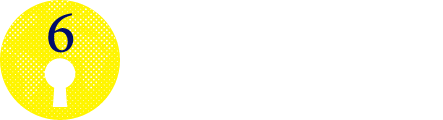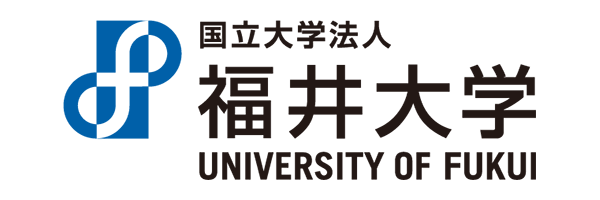チャレンジは
仲間と協力することで
より大きな成果につながる
- 国立大学法人福井大学
事務局
学務部教務課
- 代田 絢也さん
- SHIROTA Kenya
- 2019年度 国際地域学部 国際地域学科卒業
必死になって乗り越えた体験が生きる
高校時代に短期留学したアラスカで、一種の極限状態に陥りました。日本語が全くない世界で、話すことも聞き取ることも行動することもままならない孤独感と無力感。でも、それを必死になって乗り越えた体験が、進学や就職、そして今現在に至るまでのチャレンジやさまざまな壁を突破する糧になっていると感じています。
大学進学を考えたとき、自分のスキルとして英語をもっと学びたいし、大好きな地元福井の地域社会にも貢献したいという思いにぴったりはまったのが国際地域学部でした。課題探求プロジェクト(PBL)では、新商品開発によって大野市の観光を盛り上げようと奮闘しているプロジェクトに参画し、『名物の醤油カツ丼を食べ歩きながら大野市内を観光できる』をコンセプトに、地元のパン屋さんと協働して「醤油カツバーガー」を開発しました。PBLの面白いところは、グループワークだということ。一人で突っ走って新商品を開発したり、企画したりもできるのですが、グループで活動することで、メンバーそれぞれの多様な視点から課題を分析でき、一人では気づけない新たな発見やアイデアが生まれることを実感しました。そのためにも、互いの意見を尊重し、全員で協力し合うことの大切さに改めて気づかされました。地域のいろんな方との交流も、私が知らなかった福井の底力に触れる体験でした。
一人ひとりに親身になるためにRPAを積極的に導入
卒業後は、大学職員として福井大学に。でも、最初の配属先は、馴染みのある文京キャンパスではなく、松岡キャンパスにある附属病院。電子カルテのシステムやカルテのアップデートを担当することになりました。医療もシステムもこれまでの人生でまったく関わってこなかった世界だったので、必死に勉強したり、調べたりして、知識や経験をコツコツ増やし、先輩職員に追いつこうと必死でした。かつてアラスカで、自分が必死になれば何とかなる、という経験がここでも生きた感じです。病院部時代に出会ったのがRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)です。これはソフトによる作業効率を図る取り組みで、現在所属している教務課でも進んで取り入れています。課内で勉強会を積極的に開いて、システムやプログラム関係に苦手意識がある方でもRPAを活用でき、課全体として業務改善を図れるようRPAに取り組んでいます。教務課は学生と向き合う時間が多い部署です。いろんなタイプの学生がいるからこそ、一人ひとりに対して親身に接することが求められます。その時間を作るにはRPAはとても有効なのでは、と思っています。
また、今年、国際地域学部の同窓会を立ち上げ、理事長に就任しました。卒業生が集まってイベントや交流会をするだけでなく、各期の代表メンバーたちと事業計画を立て、組織作りや資金をどう集めるかなど、考えなければならないことがたくさんあります。現在、同窓会としてできる在学生向けの支援として、留学関係の支援や在学生から需要の多いキャリア支援などを考えており、それらの実現に向けて今後活動を本格化する予定です。そのためにも、若い世代が中心となってできた同窓会をこれからもっと盛り上げていきたいです。
 学生時代は、バスケットボール部でキャプテンに。
学生時代は、バスケットボール部でキャプテンに。 PBLで開発した「醤油カツバーガー」。とんかつと大根おろし、大葉を挟み、マヨネーズと地元のお醤油で味付け。
PBLで開発した「醤油カツバーガー」。とんかつと大根おろし、大葉を挟み、マヨネーズと地元のお醤油で味付け。