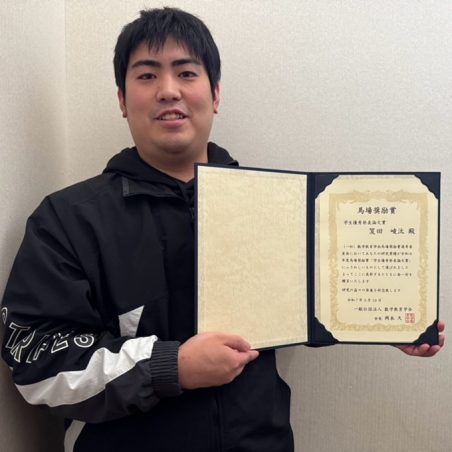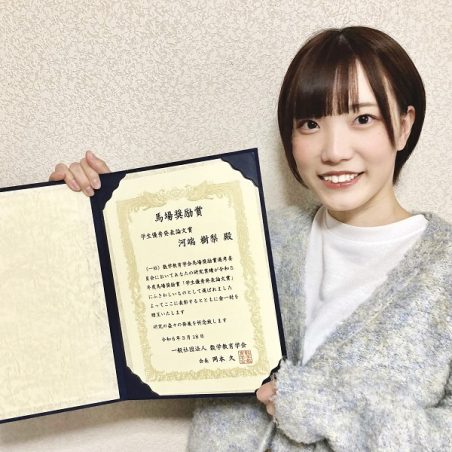受験生のためのFUKUDAI LIFE
教育学部
興味から始まる ものづくりの挑戦
研究室の隅に置かれていたクレーンゲームのアームを動かすレールのジャンク部品を見て「自分でも作れるかも」と思ったことが製作のきっかけです。 工業系の高校出身で金属加工が得意な澤﨑さんは、アルミフレームを使って骨組みを組み立てたり、配線をつ[...]
審判って面白い! 未来の教員が ピッチで学ぶこと
サッカーが大好きな出倉さん。中学1年生のとき、サッカー部の顧問の先生に声をかけられたことをきっかけに、選手としてだけでなく審判員としてもサッカーに関わり始めました。 審判員に求められるのは、どんな状況でも冷静に、そして公正・公平に判定し[...]
子どもの個性に寄り添って 一人ひとりの未来を輝かせたい
「社会モデル」という視点に衝撃を受け、特別支援教育の道へ 特別な支援を必要とする子どもたちに寄り添い、将来の可能性を広げたい―。教育学部で特別支援教育の授業を受けた時、そんな思いを持ちました。私の兄のこだわりが強い特徴に、一緒に生活してい[...]
スポーツ科学から介護予防へ
地域で暮らす高齢者のために 私は、高齢者に元気で長生きしてもらう、つまりフレイル予防の研究をしています。その一つが、寝たきりなどのきっかけとなる“転倒” を予防するための日常生活におけるリスク評価、改善プログラムの開発です。例えば、転倒予[...]
数学教育学会2025年度春季年会大学院生等発表会で学生優秀発表論文賞を受賞!
高等学校の数学では、二次関数、三角関数、指数関数、対数関数などさまざまな種類の関数を学習します。これらは、xが決まればyが決まるため、1変数関数と呼ばれます。関数はこの他にもx、yが決まればzが決まるといった2変数関数も存在します。例えば、[...]
偶然の経験を糧に 音楽を伝えることに 挑み続ける
福井大学フィルハーモニー管弦楽団で学生指揮を務める平林さん。中高と吹奏楽でクラリネット演奏をしていましたが、友達に誘われて入団し、いつのまにか学生指揮をすることに。平林さんの音楽活動は偶然の経験の積み重ねだったそうです。 中学校で楽器を[...]
哲学と教育をつなぐ推論ネットワーク
道徳教育を哲学でアプローチする 大劇場のステージに立つことを夢見る売れない手品師が、父親が亡くなり母親は働きに出ていて、寂しいという男の子に出会う。手品を見せると、男の子は元気を出し「明日も来てくれる?」と訊ね、手品師は「来るとも」と約束[...]
子どもたちが平等に 夢を叶えられる世界を 実現していく。
「支援すること」でハンディキャップを越えていける ここに通う子どもたちは、自分で1日の計画を立て、各自のスケジュールに沿ってドラムを叩いたり、パソコンを操作したり。コミュニケーションが苦手な子は、まずはここへ来ることを目標にして、どう過ご[...]
プロリーグで 活躍しながら 特別支援教育を学ぶ
笹本さんは大学院で特別支援教育を学びながら、ハンドボールチーム「福井永平寺ブルーサンダー」に所属し、プロのハンドボール選手としても活躍しています。 中学生の時、両親の勧めで地元岐阜のクラブチームに参加したことがハンドボールの世界に足を踏[...]
子どもをまんなかに 保育・教育環境をつくる
言葉は、難しい 保育の現場で勤めていたころ、子どもの育ちについて語り合う際には具体的な面白いエピソードで大いに盛り上がりました。しかし、実態や課題を理論の言葉で考察し始めると、その盛り上がりは途端に止まります。現場の出来事や課題に対して、[...]
地元の知らない 「最高」に出会うプロジェクト
大学生活もあと少し。これからは福井で仕事をしていくけれど、地元福井のことあまり詳しくないかも!? 将来を考えながらそう感じていた田島さんと山下さんは、福井県が実施する「最高!」と共有したくなる福井の魅力を発信する「ふくい最高!」プロジェク[...]
“良い授業”の開発 教育工学で
少人数クラスに「バーチャル転校生」登場 ―少人数学級のある日。「今日は転校生が一緒です」と教員が紹介して授業が始まりました。その転校生は、教員のパソコンにつながったディスプレイの画面の中。学級の生徒とは全く違った生活圏、首都圏から来たとい[...]
数学教育学会2024年度春季年会大学院生等発表会で学生優秀発表論文賞を受賞!
算数学習では、図形の求積公式や割合に関する公式など、さまざまな公式が学習対象となりますが、小学生の公式理解には問題点が指摘されています。例えば、令和5年度全国学力・学習状況調査で出題された2つの三角形の面積を比較する問題、の正答率は21.1[...]
数学教育学会2024年度春季年会大学院生等発表会で学生優秀発表論文賞を受賞!
私は教育実習で担当した中学校第1学年の「方程式」の授業中、生徒が解を求められずに困っていました。観察すると、自らが立式した方程式を解いた結果、0=0の等式に辿り着いてしまい困っているようでした。こうした方程式学習における躓きに興味を持ち、私[...]
ちえなみきを拠点に 敦賀の魅力を発信
竹越さんと岡野さんは、本学地域創生推進本部附属嶺南地域共創センターと共創し、敦賀市知育・啓発施設「ちえなみき」で行っているプロジェクトに課外活動として参加し、敦賀市の魅力発信に取り組んでいます。 敦賀高校出身の2人。竹越さんは、高校時代に[...]
垣根を越えた つながりを生む 探求ネットワーク
教育学部の学生が小学校4年生から中学生までの子どもたちと一緒に9つのブロックに分かれて活動し、企画、運営、協同、共有の4つの力を身につけることを目的とした探求ネットワーク。 大学1年生は授業として、2、3年生は有志のスタッフとして、ほぼ学生[...]
温故知新 漢文って面白い!
近代化の根底にあった“漢文” 日本は、江戸から明治へと時代が移った際、欧米列強の植民地になることなく、国際社会の仲間入りを果たした稀有な歴史を持っています。私はその基盤の一つが、江戸時代に町人を含む幅広い層に学問が普及していたことだったと[...]
一人ひとりが輝く教育の実現
多様であることを強みとして 教育現場では、今日も多様な子どもたちがともに学んでいます。その中には、学習につまずきのある子もいれば、人とのかかわりに難しさのある子もいます。特定の分野に強い関心や力を有する子もいれば、外国にルーツのある子もい[...]
芸術教育は何を育むのか
仏の“学校参与アーティスト” フランスは「芸術大国」と呼ばれています。それは著名な芸術家を数多く輩出しているから、だけではありません。長い年月をかけてさまざまな芸術が人々の生活の一部となっていて、国をあげてそれを後押しする教育・文化政策を[...]