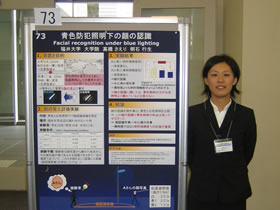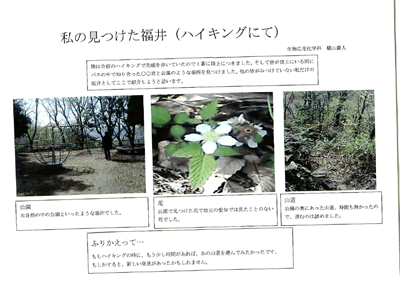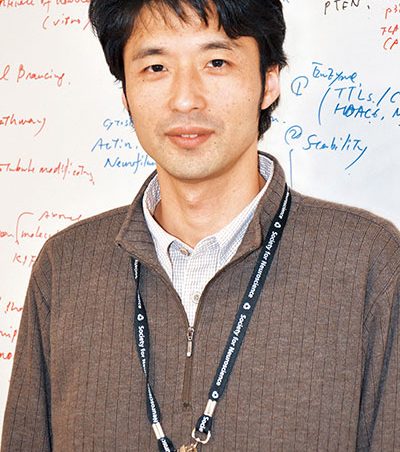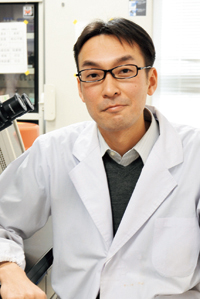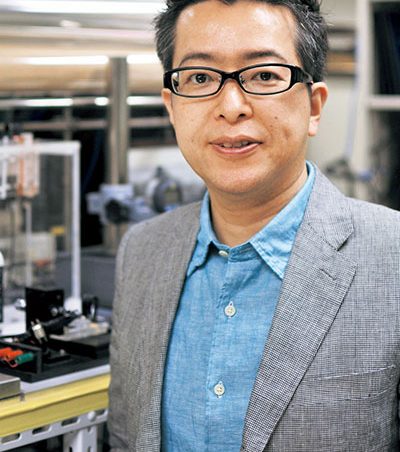受験生のためのFUKUDAI LIFE
工学部
照明学会全国大会 優秀ポスター発表者賞 受賞
平成20年度(第41回)照明学会全国大会において、「青色防犯照明下の顔の認識」のショートプレゼンテーション付きポスター発表を行った結果、工学研究科の高橋さえりさんが優秀ポスター発表者賞を受賞しました。この賞は、照明学会全国大会委員会が主催す[...]
学生発『街なか』にぎわいプラン優秀賞受賞
学生から福井県内の中心市街地の活性化策を募集する「学生発『街なか』にぎわいプラン」の選考会で優秀な企画として私たち、灯りプロジェクトが優秀賞と報奨金をいただきました。 灯りプロジェクトとは本学の建築学科をはじめとする多様な学科の修士や学部生[...]
世界カヌーポロ選手権 日本代表に選出
日本を代表するプレイを 昨年日本代表候補に選出されて以来、月に1、2度の合宿を経てこの度正式にU-21代表となりました。大学に入って1年目、高校までとは違い周りの強い先輩たちの中でもまれ、他県の強いチームと戦いあった結果が今回のことだと思い[...]
平成19年度日本生物工学会 大会トピックに選出
平成19年度生物工学会にて,工学研究科 生物応用化学専攻1年の白石智美さんが発表した演題「磁性ビーズを組み合わせた有害微生物の電気科学的高感度DNA検出システム」がバイオテクノロジーのフロンティアを象徴するトピックスとして選出され,要旨が学[...]
ロボカップ・ジャパンへの参戦
ロボカップとは? ロボカップとは、世界で最も大規模なサッカーロボットの競技大会で、1997年から毎年、競技大会と国際会議が世界各地で開催されています。私たちはこれまで、“FC-Soromons”というチーム名で、ロボカップの中の“中型ロボッ[...]
ボランティア功労者厚生労働大臣表彰受賞
本学ボランティアサークル「together」が、平成18年ボランティア功労者厚生労働大臣表彰を受賞し、1月12日(金)、学長に受賞報告を行いました。 本表彰は、福祉分野のボランティア活動、支援を長年率先して行っている者等、その功績が特に顕著[...]
ふくいソフトウエア・コンペティション2006:奨励賞受賞
コンピュータプログラム等の優秀性と先進性を競う「ふくいソフトウエア・コンペティション2006」において、工学部知能システム工学科4年 山上浩司さんが奨励賞を受賞し、10月19日(木)に開催された“ふくいITフォーラム2006”の会場で表彰を[...]
全日本学生フォーミュラ大会参戦
参戦のきっかけ 全日本学生フォーミュラ大会とは日本自動車技術会が主催し、学生が車両を設計製作し、デザイン、コスト、マシン性能を競う大会です。 私たちフォーミュラカー製作プロジェクト(FRC – Formula car Racin[...]
学生ISO委員会結成
私たち文京地区学生ISO委員会は平成18年9月下旬に結成しました。教育地域科学部の地域環境コースから約10人、工学部(主に生協の学生委員会)から約10人という20人以上の人が集まりました。私たちは地球環境、自然環境、リサイクルなどに大変興味[...]
2006福井県デザインコンクールグランプリ受賞
今年で32回を迎える福井県デザインコンクールにおいて、本学建築建設工学科4年 住田薫さんがグランプリを受賞しました。 「環境」「世界平和」を題材とするテーマ部門、自由課題、イラスト・漫画の3部門に166点の応募があり、住田さんは自由課題部門[...]
RoboCup2006 SimulatlonLeague Development Competition 3位入賞
6月14日~20日まで、ドイツ・ブレーメンで開催されたRoboCup2006において、本学大学院工学研究科知能システム工学専攻 瀧澤 崇さんと仁愛大学助手 久保長徳さん(本学大学院修了)のチーム“JU-TSUBAMEGAESHI”が、世界各[...]
超微量分析で環境保全に貢献
汚染物質を早期に発見 学生と実験中 事故や災害により工場などから漏れ出た有害物質は、時間の経過とともに生態系の破壊や健康被害といった重大な問題を生むかもしれません。そのため、ごく微量なレベルで環境汚染物質を早期に発見し、対策を講じることが重[...]
誰もが持っている楽器“口笛”世界初!口笛検定開始!
口笛吹けますか? 近年、国内で定期的に「口笛音楽コンクール」が開催されるようになり、コンクールで上位入賞を果たすなどの活躍をした口笛奏者によって、「口笛音楽教室」が開講されるようになりました。また、口笛愛好家が定期的に集まり練習する「口笛音[...]
脳神経細胞を形づくるシステム
生体から学ぶ 今、知能システム工学専攻では、多くの人にとって使いやすく、柔軟なマルチメディアやメカトロニクスをどのように作るかということを課題としています。その一つのアプローチとしてヒトや生物の知能から学ぶことで、これに基づいた新しいシステ[...]
『型にはまらない』加工技術
コンパクト、省エネの裏側 皆さんが使っている携帯電話やデジタルカメラなどは、5年前のものと比べてみると、ずいぶんと小さくなって、様変わりしています。こうしたデジタ ル製品の小型化が進むと、中の部品はどのくらいの大きさになっているのか、想像が[...]
目尻の小じわを工学的に解き明かす
「お肌の曲がり角」を科学する 肌の曲がり角といっても、学生の皆さんはまだ感じたことがないでしょう。ここでの話は、年をとると突然現れるという「小じわ」の話です。年齢を重ねると、なぜ皮膚の形が変わるのでしょうか? 私は機械工学の研究者で、構造力[...]
繊維で表現する 組織の立体構造
広がる繊維の可能性 私が所属する専攻はこの4月からファイバーアメニティ工学専攻から繊維先端工学専攻となり、文字通り繊維技術に特化した研究を行っています。近年では、ひと言に繊維といっても、最先端の航空機や車のボディに使われ、鉄の変わりにもなっ[...]
現在の工学的な「動き」の限界を乗り越える
創造力への挑戦 2011年の東日本大震災で、調査や修復ロボットがテレビ報道で話題になりました。国産ロボットかと思いきや、米国企業の製品紹介の絶好の機会に化しました。日本は改良は得意でも創造力がなかった。前例の無い、世の中に役立つものを作る創[...]